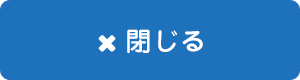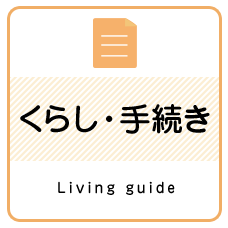介護保険利用者負担限度額認定について
施設サービス(ショートステイを含む)を利用されている方の居住費や食費は基本的に全額利用者負担となります。ただし、これにより低所得者の施設利用が困難とならないよう、世帯全員が市民税非課税の方は負担額の減額を受けることができます。
負担限度額の認定を希望される方は、申請が必要です。認定を受けられた場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービスを受ける際には、必ず入所施設等に提示してください。
対象となる施設サービス
居住費(滞在費)と食費の軽減対象となる介護サービスは以下のとおりです。
- 施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
軽減の対象となる方は?
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
- 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること。
- 同一世帯に属さない配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税であること。
(配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます) - 預貯金等の資産の合計額が、該当する利用者負担段階の基準額以下であること。
※預貯金等とは利用者とその配偶者が所有する現金、預貯金、合同運用信託、公募公社等運用信託及び有価証券その他これらに類する資産をいいます。
利用者負担段階と負担限度額
利用者負担段階
|
利用者 負担段階 |
対象者 | 預貯金等の資産の合計 |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 |
住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(※1)収入額の合計額が年間80.9万円(※2)以下の人 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階(1) | 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(※1)収入額の合計額が年間80.9万円(※2)超、120万円以下の人 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階(2) | 住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(※1)収入額の合計額が年間120万円超の人 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
| 第4段階 (対象になりません) |
・世帯内に市民税を課税されている人がいるが、本人が市民税非課税の人 ・本人が市民税を課税されている人 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
(※1) 第2段階・第3段階(1)(2)については、非課税年金(遺族年金や障害年金等)の収入額も含めての判定となります 。
(※2) 「80.9万円」の記載は、令和7年8月からの適用となります。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。(介護保険法施行令改定による)
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合は、第2段階・第3段階(1)(2)の方は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です。
利用者負担段階で「特例減額措置」を受けられる人
利用者負担第4段階の人は、「介護保険負担限度額認定」の対象とはなりません。
しかし、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで生計が困難になるなど一定の要件を満たし、申請により認められた人は利用者負担第3段階と同様の「特例減額措置」を受けることができます。
負担限度額(1日あたり)
一日あたりの負担限度額
|
利用者 |
居住費(滞在費) |
食費 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 |
||
|
第1段階 |
880円 |
550円 |
550円 |
0円 |
300円 |
|
第2段階 |
880円 |
550円 |
550円 |
430円 |
390円 |
|
第3段階(1) |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
650円 |
| 第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 |
430円 |
1,360円 |
※ 従来型個室の( )の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。食費の( )の金額は、短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合の額です。
注意:実際の費用は、施設との契約によって決められます。
負担限度額認定の申請
申請書に必要事項を記入したうえで、必要な書類を添え、本人または家族が申請してください。
提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 通帳等の写し(本人名義の預貯金・有価証券・株式など)
- 配偶者「有」の場合は、配偶者名義のものも必要です。
- 市役所でコピーできますのでお持ちください。
提出先
中央市役所本庁 長寿推進課
※玉穂、豊富支所では受付ができません。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 長寿推進課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125
メールでのお問い合わせはこちら