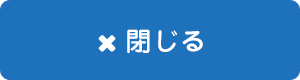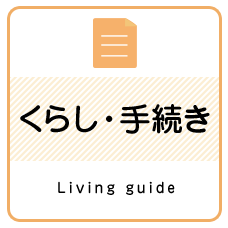不妊治療
不妊治療費等助成について
不妊症により子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療に対する助成をしています。
平成29年度からは「特定不妊治療」(体外受精および顕微授精)に限らず「一般不妊治療」(タイミング法、人工授精、検査・診察、画像診断・処置、投薬等)を行った場合も含めて助成が受けられるようになっています。
また、男性不妊治療についても助成を行っています。
対象者
以下の3つの要件を全て満たす方
・治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦であり、どちらか一方または双方が、不妊治療費助成金の申請日において本市に1年以上住所があること。 ※転入して1年未満の場合は申請できません。
・医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療(タイミング療法、人工授精、検査・診察、画像診断・処置、投薬治療等)や特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、男性不妊治療を行っていること。
・夫婦共に市税および国民健康保険料等を滞納していないこと。
助成金の額
一般不妊治療及び特定不妊治療
1回の治療に要した医療費の自己負担額の1/2の額(上限10万円)
※高額療養費や付加給付、他の地方公共団体の助成事業(山梨県等)などで給付を受けた場合は、その額を控除した額が申請の対象になります。本市に申請する際は医療保険者等からの助成額を確認してから申請書を提出してください。
なお高額療養費や付加給付等は、払い戻しまでに3ヶ月以上かかり、通知書が郵送されない場合もありますので、ご注意ください。
男性不妊治療
当該不妊治療に要した医療費の自己負担額の1/2の額(上限5万円)
助成回数
1子ごとの不妊治療につき1年度に2回まで、通算5か年度
※本市にて不妊治療費の助成を受けて出産した場合、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。(令和4年度以降の不妊治療に係る助成金について適用)
※継続して何回かの治療を受けている場合、まとめて1回の治療と考えて差し支えありません。ただし医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合は、その時点で一旦治療が終了したものと考えます。
申請方法
治療が終了した日から起算して1年以内に、申請書等の提出書類を揃えて、健康増進課へ提出してください。
※令和5年4月1日以降に開始した治療が対象です。
提出書類
1 中央市不妊治療費等助成金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)
2 中央市不妊治療費等助成金受診証明書(様式第2号)
3 医療機関(薬局含む)等が発行する不妊治療費等に係る領収書及び診療明細書(原本)
4 他の地方公共団体が実施する不妊治療等に係る支援等を受けている場合は、その承認通知書等の写し
5 高額療養費及び附加給付金に関する通知書の写し
※令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診察 を受ける際はマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みとなりました。それに対応し、様式1号・様式2号および提出書類が変更しています。
※なお令和7年3月末までは旧様式での申請も受け付けますが、その場合は、夫婦共に加入保険の資格が確認できる書類(保険証またはマイナンバーカード)の写しをご提出ください。
※ご加入の保険資格や限度額適用認定はマイナンバーカード(マイナポータル)でご確認ください。なおマイナンバーカードを取得していない方や、保険証として登録していない方は、加入している医療保険者から「資格確認書」の交付を受けてください。
※「高額療養費」「限度額適用認定書」「付加給付金」については、加入している医療保険により異なりますので、詳細は各保険者にお問い合わせください。
※申請には領収書及び診療明細書の原本が必要です。無くされた場合、助成できかねますのでご注意ください。
申請書を提出する場合は、事前に健康増進課(担当者)へご連絡の上、お越しいただけますようお願いいたします。また申請から支給までには期間を要しますので、ご理解をよろしくお願いいたします。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども健康部 健康増進課 母子保健担当(こども家庭センター)
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8542
ファックス:055-274-1125