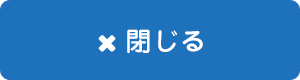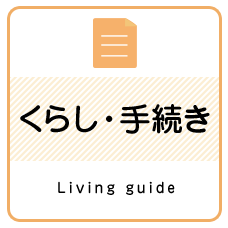高額療養費制度について
高額療養費の支給申請
病気や怪我で医療機関に受診した時は、保険証または資格確認書を提示することで、かかった医療費のうち自己負担分(2~3割)を支払うだけで医療を受けることができます。残り(7割~8割)は国民健康保険から療養の給付として医療機関へ支払われています。
しかし、病院に長期間入院したり、手術などで高額な医療を受ける場合には、たとえ医療費のうちの自己負担分だけとはいえ、高額になってしまう場合があります。 このような場合に被保険者の負担を軽減するため、自己負担額に上限が設けられています(自己負担限度額)。この自己負担限度額を超えた分の医療費が後日返還されるしくみを高額療養費制度といいます。
※該当する世帯には、通常、診療月の翌々月に市役所から通知と一緒に申請書を送付します。
※高額療養費を申請できる期間は医療費を支払ってから2年間です。
申請受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
- 市役所本館 保険課
- 玉穂支所
- 豊富支所
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書 ※該当世帯には申請書を送付します。
- 治療費の領収書
- 世帯主のマイナンバー確認書類
- 来庁される人の本人確認書類
- 委任状(別世帯の人が代理申請する場合)
自己負担限度額について
70歳未満の人
|
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 (過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。) |
| 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+ (総医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
| 基礎控除後の所得 600万円超〜901万円以下 |
167,400円+ (総医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
| 基礎控除後の所得 210万円超〜600万円以下 |
80,100円+ (総医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
| 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
|
所得区分 |
外来 |
外来+入院の限度額 |
||
|
現役並み |
I |
課税所得 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
|
II |
課税所得 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||
|
III |
課税所得 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
|
一般 |
18,000円 144,000円 |
57,600円 44,400円※1 |
||
|
低所得者II ※2 |
8,000円 |
24,600円 |
||
|
低所得者I ※3 |
15,000円 |
|||
※1過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目からは「多数回」該当となり限度額が下がります。
※2 世帯全員が非課税であり、低所得者I以外の世帯となります。
※3 世帯全員が非課税であり、世帯全員の所得が0円(年金収入のみの方は受給額80万円以下)の世帯となります。
計算上の注意点
月の初日から末日までの診療分を1か月として計算します。
差額べッド代など保険がきかないものや、入院時の食事代・居住費は対象になりません。
70歳未満の人の場合
70歳未満の人の場合は、次の通り別々に計算し、21,000円以上のみを合算します。
- 医療機関ごとに別計算します。
- 一つの医療機関でも、入院・外来・歯科は別々に計算します。
- 院外処方の場合、医療機関と薬局を1つの医療機関とみなします。
70歳から74歳までの人の場合
全ての一部負担金を合算します。
医療機関などでの支払いが自己負担限度額までとなる制度(現物給付)
一つの医療機関で1か月の自己負担額が自己負担限度額を超える場合、その超える額を中央市から医療機関に直接支払い、被保険者の窓口での負担が自己負担限度額で済む制度があります。
この取り扱いを受けるためには、「限度額適用認定証」(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証または資格確認書と併せて医療機関に提示する必要があります。
申請受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
- 市役所本館 保険課
- 玉穂支所
- 豊富支所
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 保険証または資格確認書
- 印鑑
- 世帯主、対象者のマイナンバーのわかるもの
- 来庁される人の本人確認書類
- 委任状(別世帯の人が代理申請する場合)
- 住民税非課税世帯において過去12ヶ月以内に90日以上入院していた場合は治療費の領収書等入院期間がわかる書類
※「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月の初日から有効になります。
※世帯の国保加入者全員が住民税非課税の世帯については、証を提示することによって食事負担分も軽減されます。
※国民健康保険税に未納がある世帯では利用できないことがあります。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら