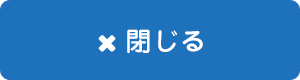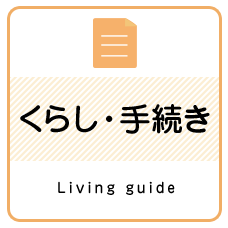児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚、父母いずれかの死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者
次の1~6のどれかの条件に当てはまる児童を監護している「母」、児童を監護し生計を同じくする「父」、または父・母にかわって児童を養育している方(養育者)。
手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで(例えば、児童の18歳の誕生日が4月9日の場合は、翌年3月まで)支給されます。
但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級(一部)、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障がいを有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。(申請手続きが必要です。)
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(おおよそ身体障害者手帳1、2級)の障がい状態にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄(父また母が児童と同居しておらず、金銭的に仕送りなどなく、訪問・手紙・電話等がない状態)されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている(刑務所に在監等)児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
次の場合、手当は支給されません
- 申請者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に養育されているとき
- 公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方で年金額が児童扶養手当額よりも高いとき。(低いときはその差額分が支給されます)
支給制限
児童扶養手当の月額は、前年(1~10月分の手当については前々年)の所得額に基づいて決定されます。手当を請求する方の所得が制限限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止になります。また、手当を請求する方の配偶者や扶養義務者(同居している申請者の父母兄弟姉妹など直系血族)の所得が制限限度額以上である場合は、全額支給されません。
※毎年11月から翌年10月までを支給年度とし、支給年度単位で手当の額を決定します。
所得制限限度額
・給与所得の場合は、給与所得控除後の額
・所得には養育費等の8割相当額を加算します
・扶養親族の数は原則課税台帳上のものになります。申請時点での扶養人数ではありません
| 区分 | 扶養親族の数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 父親又は母親及び養育者の所得 | 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | |
| 扶養義務者及び孤児等の養育者の所得 | 0人 | 2,360,000円 | - |
| 1人 | 2,740,000円 | ||
| 2人 | 3,120,000円 | ||
| 3人 | 3,500,000円 | ||
| 4人 | 3,880,000円 | ||
| 5人 | 4,260,000円 |
手当額
所得額による支給制限が設けられており、受給資格者及び同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の所得状況により、全額支給、一部支給停止又は全額支給停止に区分されています。
所得制限額は、税法上の扶養親族数等により異なります。詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
令和7年4月分から支給額が下記のように変更となります。
全部支給
月額
第1子 46,690円
第2子以降加算額 11,030円
一部支給
月額
第1子 46,680円 ~ 11,010円
第2子以降加算額 11,020円 ~ 5,520円
《参考》一部支給額の計算式(令和7年4月以降)※10円未満は四捨五入し、10円単位で決定します。
第1子
46,680円―((母(父)及び養育者の所得額〔※1〕―所得制限限度額〔※2〕)×0.0256619〔※3〕)
◆第2子以降
10,020円―((母(父)及び養育者の所得額〔※1〕―所得制限限度額〔※2〕)×0.0039568〔※3〕)
〔※1〕所得金額に父又は母及び児童が受け取る養育費等の8割相当額を加算し、児童扶養手当法施行令により定められた控除額を差し引いた額です。
〔※2〕所得制限限度額は、上記の表に定める父親又は母親及び養育者の全部支給欄の所得制限限度額です。
〔※3〕月額、一部支給額を算出するための係数は、物価指数の変動により定期的に改定されます。
※実際の支給額は、所得の審査などによって決定します。控除など法令で細かく規定されていますので、あくまでも目安としてください。
支払い月
手当の申請が受理された日の翌月から対象です。
奇数月の11日に前々月と前月の2か月分を支給します。
(支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日の支給となります。)
手続きについて
認定請求
手当を受けるためには、認定請求書を提出する必要があります。
申請書類は、手当を受ける方の状況によって必要書類が異なり、また個人情報に係る相談内容となることから、電話等でのお問い合わせではご案内が難しいため、子育て支援課(市役所本館)に来庁のうえ相談してください。
なお、来庁の際は、相談及び申請に多少時間がかかるため、事前に電話予約をして、時間に余裕をもってお越しいただくようお願いいたします。
申請等は、子育て支援課(市役所本館)でしか受付ができませんのでご注意ください。
現況届
児童扶養手当の認定を受けたときは、毎年8月1日から8月31日の間に 「現況届」 を提出しなければなりません。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
7月下旬に現況届を送付しますので、必ず8月中に提出してください。(所得制限により手当の支給が停止されている方も提出が必要です。)
現況届未提出のまま2年を経過すると、時効により支給を受ける権利がなくなります。
注意事項!!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず「資格喪失届」を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻をしなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくともひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある、社会通念場夫婦と思われる場合など)になったとき
- 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
- 児童が、児童福祉施設に入所したり、婚姻や転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含む)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども健康部 子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
メールでのお問い合わせはこちら