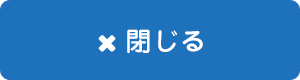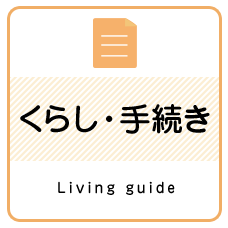地域生活支援拠点事業
地域生活支援拠点の概要
地域生活支援拠点は、障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活で生じる障害者やその家族の緊急事態に対応するための体制を整備するものです。
この事業は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づくものです。
事業の目的
地域生活支援拠点の整備には、次の2つの目的があります。
- 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施、短期入所等の障害福祉サービスを活用することにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
- 入所施設や親元から共同生活援助(グループホーム)や一人暮らし(アパート)等へと生活の場を移行しやすくなるように、体験の機会の提供等の支援体制を整備することにより、障がい者等の地域での生活を支援する。
国は、地域生活支援拠点の機能強化を図るため、次の2つの整備方法をイメージとして示しています。
- 5つの機能を集約し、グループホームや障がい者支援施設等に付加した「多機能拠点整備型」
- 地域における複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」
中央市では、 面的整備型での整備を進めています。
必要な5つの機能
地域生活支援拠点の整備を進めるうえで、次の5つの機能の強化が必要とされています。
| 機能 | 必要な主な機能の内容 |
| 相談 | コーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 |
| 緊急時の受入れ・対応 | 短期入所等の障害福祉サービスを活用した常時の緊急受入れ体制を確保した上で、介護者の急病や障がい児者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 |
| 体験の機会・場の提供 | 施設や病院からの地域移行や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
| 専門的人材の確保・育成 | 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい児者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行う機能 |
| 地域の体制づくり | 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、それらを提供できる地域の体制整備等を行う機能 |
中央市では相談機能を担うコーディネーターを、中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」が行っています。
中央市・昭和町障がい者相談支援センター 穂のか
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地5
電話:055-274-1100
ファックス:055-274-1103
メールでのお問い合わせはこちら
中央市地域生活支援拠点登録事業所の一覧
現在の中央市地域生活支援拠点登録事業所は、次の通りです。(令和5年4月1日現在)
地域生活支援拠点登録事業所一覧 (PDFファイル: 544.1KB)
地域生活支援拠点事業利用の登録について
緊急時の対応が必要だと考えられる対象者については、緊急時の短期入所等による受け入れなどを円滑に進めやすくするために、事前に利用登録を行うことができます。
登録に必要な書類
- 事前登録届出書
- 緊急時サポートシート
記載にあたっては、コーディネーターや相談支援専門員とご相談の上、作成してください。
緊急時サポートシート(記入方法) (PDFファイル: 342.5KB)
受付窓口
中央市役所 福祉課 障がい福祉担当
玉穂支所・豊富支所では受付できませんのでご注意ください。
※拠点の利用対象者は、原則18歳以上65歳未満の障がい者で、以下のいずれかの条件に該当する方となります。
- 同居者が高齢、障がい又は疾病等のため、同居者の緊急時に対象者の支援が行えない者
- 同居者が1人のため、同居者の緊急時に対象者の支援が行えない者
- 対象者が単身世帯
- 対象者とその親のみで構成される世帯で、「親亡き後」の生活は障がい福祉サービスの利用が予想される者
地域生活支援拠点の登録について(事業者向け)
中央市の地域生活支援拠点の機能を担う事業所として届出を行うと、国保連請求にて各種加算を算定することができる場合があります。詳細は下記のページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 福祉課 障がい福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125